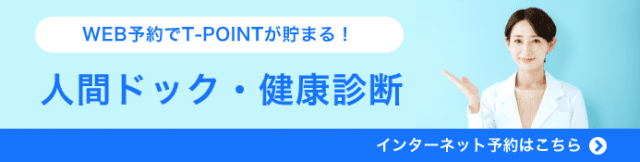

ひとりひとりのこころと向き合い、通じ合うやすらぎの医療をめざして
大垣中央病院は大垣市に根づく総合病院として、つねに医療の原点に立ちかけがえのないいのちを守り、愛し、育んでいきたいと考えます。
病院の概要
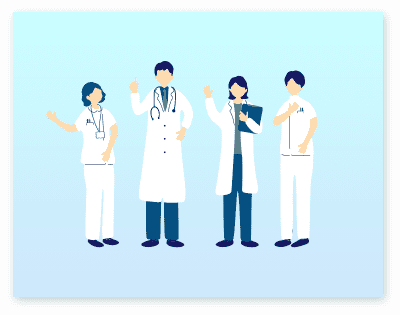
概要や沿革、指定医療機関などの基本情報をご紹介します。
外来のご案内
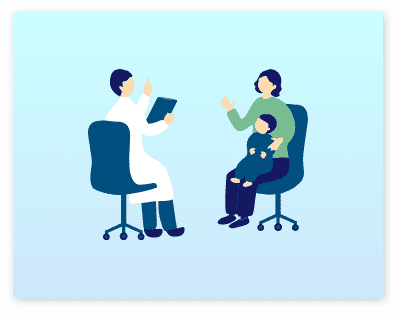
診療科目、診療時間・休診日、受付時間、予約などのご案内です。
入院のご案内
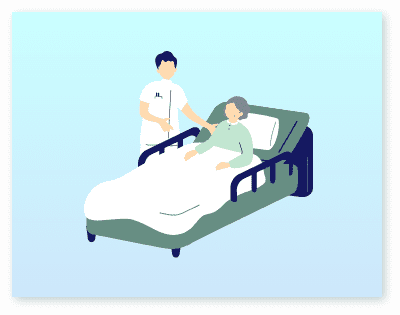
入院手続き、持ち物、寝具・食事、面会時間などのご案内です。
Infomationご案内




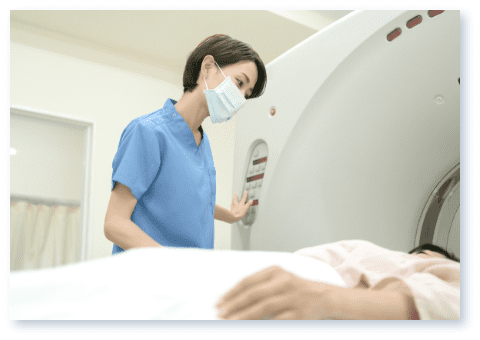
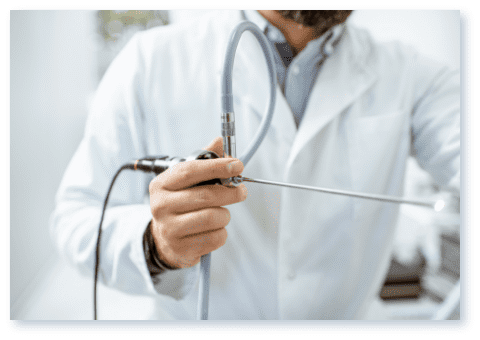
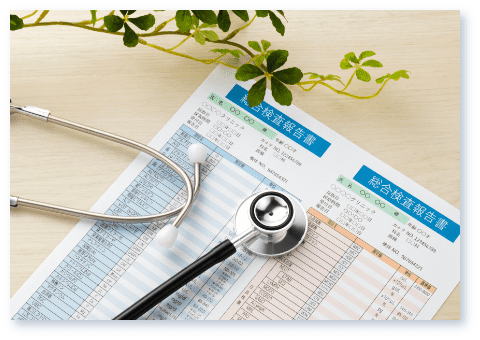
Recruitment採用情報

当院では豊かな経験や知識をもつ人はもちろん、スタッフとともに自分自身で何かを成し遂げたいと考えているエネルギーに満ちあふれた人材を募集いたしております!


accessアクセス
医療法人社団豊正会 大垣中央病院
| 住所 | 〒503-0025 岐阜県大垣市見取町4丁目2番 |
| 電話 | TEL 0584-73-0377 FAX 0584-73-8380 |
| 駅 | JR大垣駅より徒歩5分 |
| 診療科目 | 内科、外科、整形外科、リハビリテーション科、消化器内科、消化器外科、循環器内科、泌尿器科、肛門外科、糖尿病内科、腎臓内科、リウマチ科 |
